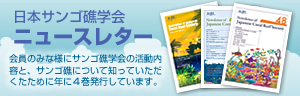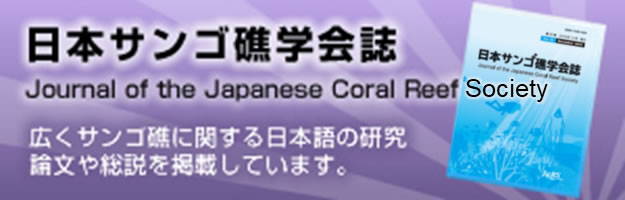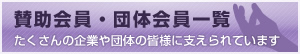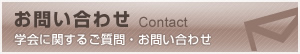調査安全委員会
設立の趣旨
サンゴ礁調査安全委員会は、サンゴやサンゴ礁に関する野外での調査・研究に伴う会員の事故防止や安全管理意識の向上を目的として、2001年11月1日に設立されました。主な活動内容は、会員から寄せられた事故の事例,各種研究機関の事故防止策や安全管理体制といった情報を収集・整理し、それらをまとめた結果を年会・ニュースレター・学会ホームページといった学会に関する様々な媒体を通して会員に提供するというものです。こうした情報をもとに会員である私たち一人一人が、事故防止や安全管理に心がけて野外での作業や調査を行うことは、学会全体での事故防止や安全管理意識の向上だけでなく、日本でのサンゴやサンゴ礁の野外調査・研究能力のレベルアップへとつながります。本委員会は、寄せられた意見や情報を交換・共有する機会を積極的に提供することによって、学会から一人として事故者を出すことのないよう努力していきたいと考えています。
日本サンゴ礁学会 調査安全委員会一同
組織
調査安全委員会は、大学教員、大学付属機関や公的研究機関の研究員、そしてNPO法人の役員といった様々な職に従事する以下のメンバーによって構成されています。これらの構成員が、活動内容の決定、そしてsangoメーリングリストや学会ニュースレターおよびこのホームページにおける調査安全に関する掲載記事の選定や作成などを主に行っています。私たちの活動に賛同される方もしくは興味をもたれた方などいらっしゃいましたら、ご連絡ください。一緒に活動していきませんか?
安全委員会構成員
委員長 鈴木倫太郎
菅 浩伸、中井達郎、中野義勝、中村崇、目崎拓真、山野博哉(敬称略、五十音順)
主な活動内容
・野外調査中の事故防止や安全管理に役立つ情報の収集と紹介
・安全に関する講習会の開催
・調査安全に関する課題の共有や、解決に向けた検討 など
■これまでの主な活動
2002年1月:「第一回調査ダイビングにおける事故防止と安全管理に関するアンケート」の実施
2002年10月:公開ディスカッション「調査ダイビングにおける事故防止と安全管理-アンケート結果をもとに-」の開催
2003年1月:事故防止に向けての呼びかけ(学会ニュースレター16号)
2003年7月:事故防止に向けての呼びかけ(学会ニュースレター18号)
2004年4,8月:海洋科学技術センターでの潜水技術研修の紹介(学会ニュースレター21号, 22号)
2004年11月:「第二回調査ダイビングにおける事故防止と安全管理に関するアンケート」の実施
2005年4月:事故防止に向けての呼びかけ(学会ニュースレター25号)
2005年11月:公開ディスカッション「東京大学における潜水作業中の死亡事故について」の開催
2006年11月:学会ホームページ内に調査安全委員会のページを作成
2018年11月:日本サンゴ礁学会自由集会にて公開講演会「潜水調査における危険回避と安全管理」開催
2022年5月:潜水調査、安全に関する資料収集
関連ウェブサイト・書籍など
ここでは、野外調査中の事故防止や安全管理に役立つ情報を紹介していきます。現状では、紹介できる情報はわずかですが、今後もこれらの関連情報が集まり次第、随時更新していきたいと思いますので、お薦めのサイトや書籍などありましたらご連絡ください。
〇書籍等
| タイトル | 著者 | 出版 | 出版年 | 金額 |
| 潜水事故に学ぶ安全マニュアル100 | 後藤ゆかり | 水中造形センター | 2,000円+税 | |
| フィールドワークの安全対策(FENICS 100万人のフィールドワーカーシリーズ9) | 澤柿 教伸 編 野中 健一 編 椎野 若菜 編 |
古今書院 | 2020 | 本体3,400円+税 |
| 事例から学ぶ潜水事故対策~潜水事故を防ぐために~ | 竹内 久美 | 東京法令出版 | 2016 | 2,200 円+税 |
| 潜水作業マニュアル【Ver.1】 | 国土交通省港湾局監修 | 一般社団法人日本潜水協会 | 一般販売価格 9,000 円(消費税・送料込) | |
| 潜水作業安全施工指針(改訂版) | 国土交通省港湾局監修 | 一般社団法人日本潜水協会 | 一般販売価格 3,000 円(消費税・送料込) | |
| 港湾工事における潜水作業リスクマネジメントマニュアル〔CD付〕 | 国土交通省港湾局監修 | 一般社団法人日本潜水協会 | 一般販売価格 1,500 円(消費税・送料込) | |
| レジャー・スキューバ・ダイビング―安全潜水のすすめ | 日本海洋レジャー安全振興協会 | 成山堂書店 | 2005 | 1,800円+税 |
| スキンダイビング・セーフティ(2訂版) | 岡本美鈴・千足耕一・藤本浩一・須賀次郎 共著 | 成山堂書店 | 2019 | 1,800円+税 |
| ダイビング事故とリスクマネジメント | 中田 誠 | 大修館書店 | 2002 | 2,800円+税 |
| 忘れてはいけない ダイビングセーフティブック | 中田 誠 | 太田出版 | 2008 | 1450円+税 |
| 誰も教えてくれなかったダイビング安全マニュアル | 中田 誠 | 太田出版 | 2002 | 1550円+税 |
| 事故を起こさないための潜水医学 | 大岩 弘典 | 水中造形センター | 2007 | 4180円 |
| 海で死なないための安全マニュアル100 | マリンダイビング編集 | 水中造形センター | 2003 | 2200円 |
| 有識者15人が考える安全ダイビング提言集 | PROJECT SAFE DIVE | 日本財団 | 2017 | PDF DL無料 |
| 潜水医学講座 ~潜水事故を防ぐには~ 第7回 日本高気圧環境・潜水医学会 中国四国地方会 市民公開講座資料 |
日本高気圧環境・潜水医学会 | 第7回 日本高気圧環境・潜水医学会 中国四国地方会 市民公開講座資料 | 2016 | PDF DL無料 |
| ダイビング事故の法的責任と対策~プロダイバーのビジネスリスク | 中田 誠 | 商品スポーツリスク研究会 | 2014 | ¥ 3,000(Oceana HPにて) |
| 海のもしもにそなえよう。SAFE DIVE handbook | 特定非営利活動法人Project Safe Dive | 株式会社オーシャナ | 2018 | 1,000円(PDF版700円) |
| 7日間マスター 潜水士試験 合格テキスト+模擬テスト | 二見 哲史 | 弘文社 | 2019 | 2,200円 |
| 潜水士テキスト 送気調節業務特別教育用テキスト | 中央労働災害防止協会 編 | 中央労働災害防止協会 | 2021 | 2,750円 |
| 最新ダイビング用語辞典―安全管理、活動の実例から医学、教育情報まで | 日本水中科学協会 | 成山堂書店 | 2012 | 5,400円+税 |
〇インターネットサイト
| サイト名 | 運営 | 概要 |
| 厚生労働省 職場の安全サイト | 厚生労働省 | 過去の労災関係の情報(潜水事故)が検索可能。 |
| ダイビングで死なないためのホームページ | 個人サイト(直接リンク要注意) | スクーバ (スキューバ) ダイビングの事故の実態を知って 予防するための情報サイト |
| Marine Diving web 安全ダイビング | Marine Diving | 水事故やダイビングトラブル、潜水医学(ダイビング医学)に関する情報サイト |
| PROJECT SAFE DIVE | NPO法人 PROJECT SAFE DIVE | ダイビング事故を防止するため、安全ダイビングに有益な情報発信、施策を行う団体のHP. ダイビング事故情報も有。 |
| ウォーターセーフティガイド | 海上保安庁 | ウォーターアクティビティの総合安全情報サイト |
| みんなの海図 | マリーンネットワークス株式会社 | WEB上で閲覧可能なパソコン用海底地形図 |
| 海難発生情報(海上保安庁) | 海上保安庁 | 海難事故の発生状況の情報サイト |
| BSACビデオ教材 | BSAC | 陸上での器材セッティングから、中性浮力やトラブル対処などの実践的なスキルまで、動画を使ってわかりやすく紹介するサイト |
| 潜水救急ネットワーク(JCUE) | 日本安全潜水教育協会 | 安全で楽しめるダイビング技術の振興や、救急法・救助法の普及及び啓発などの事業のほか、環境保全活動や環境教育を行う団体の活動、情報サイト |
| 船舶事故ハザードマップ | 運輸安全委員会 | 過去の船舶事故の情報が検索できるサイト。注意喚起情報や分析、提言などの情報提供も。 |
| 海難事故発生状況 | 第11管区海上保安部 | 海難事故の事故情報サイト |
| 外国人ダイバーを雇用して潜水業務を行わせるには | 厚生労働省 | 外国人等に対する潜水士免許の付与についての情報サイト |
| OIST field activities manual | 沖縄科学技術大学院大学 | OISTのフィールド活動についてのマニュアル |
| American Academy of Underwater Sciences (AAUS) | AAUS | アメリカ水中科学アカデミーのHP |
| 日本高気圧環境・潜水医学会 | 一般社団法人 日本高気圧環境・潜水医学会 | 全国の高気圧酸素治療施設、高気圧医学専門医、高気圧酸素治療専門技師の一覧が掲載されている。ただし、2022年4月28日付けで「第2種・第1種(減圧障害対応)HBO装置情報」は休止している(2022年5月31日現在)。 |
〇ダイバー保険
| 団体 | サイト |
| DAN JAPAN | https://www.danjapan.gr.jp/service/insurance |
| PADI ダイバーズ保険(損保ジャパン) | http://www.padi.co.jp/visitors/insure/index.asp |
| 遠井保険事務所(AIU) | http://www.toy-hoken.co.jp/kojin/divers/ |
〇事故事例
| 年 | 場所 | 情報源 | 情報サイトURL |
| 2006年 | 八丈島 | 東京大学 | https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400008391.pdf |
| 2007年 | 屋久島(河川) | 九州大学 | https://www.kyushu-u.ac.jp/f/30272/20170331-1.pdf |
| 2016年 | 沖縄県 | OIST | https://www.oist.jp/ja/news-center/news/2016/11/18/27851 |